|
話題一覧へ |
循環の感性を育む「田んぼの学校」―環境教育活動としての可能性を展望する―
宮元 均
7.環境教育活動としての「田んぼの学校」の可能性について考える
(1) 「田んぼの学校」の提唱の背景と高い社会性
1998年,昨年からの少年による凶悪事件の続発に,子どもたちを取り巻く社会に何か問題が潜んでいるのではとの思いが漂っていました。そのようななか、学校教育分野では,文部省がゆとりのなかで特色ある教育を展開するために「生きる力」を育成する総合的な学習を計画し,また環境教育分野では,各省レベルでふれあい自然塾(環境省)などの事業をスタートさせ、民間レベルでも1997年に日本環境教育フォーラムが設立されるなど,自然とのふれあいを通じた環境教育活動を推進する動きが活発になっていました。さらに,農業分野では,1998年のOECD大臣会合などで,農産物貿易などに関する政策的観点から,農業を生産だけで見るのではなくて,景観や国土保全や再生可能な自然資源といった外部経済効果を農業の多面的機能として評価する議論が活発化し*14,これまで農村の活性化やレクリエーション活動などとして行われていた農村の体験活動は情操教育機能として位置づけられるとともに*15,農村の基盤を整備する農業農村整備事業における環境配慮の取り組みが活発になっていました。 (2) 代表的な2つのプログラムの果たした役割は大きい 「田んぼの学校」が扱う農業プログラムは,現在行われている機械化体系に基づく農業ではありません。昭和30年代にはまだ普通の農業として行われていた機械化される前の農具を使った人力による農業です。しかし,農具を使った農業には,人間が有史以来培ってきた農を通じた自然との原初的なかかわりを思い起こさせてくれる要素が凝縮されています。また, 2001年農林水産省とACRESが環境省と協力して始めた「田んぼの生き物調査」は,農村での生物調査を一般化させ,多くの「田んぼの学校」でも自然環境観察プログラムとして定着しました。この調査は,自然と触れ合いながら生き物の生息状況を確認するもので,地域によっては調査結果の意義も大きいものです。このように食・農軸と自然・環境軸に対応した活動のプログラムとして,「環境保全型農業」と「田んぼの生きもの調査」の代表的な2つのプログラムが確立したことが,「田んぼの学校」の内容を環境保全的で完成度の高いものとし,参加者に総合的で深みのある充足感をもたらといえます。 (3) 「田んぼの学校」によって循環の担い手を育成する 自然や環境に対する意識は,農村住民より都市住民の方が強く,また,農家より非農家の方が強いのが特徴です*16。都市住民や非農家である参加者は、潜在的に自然体験に関心の深い消費者であり,「田んぼの学校」に参加することによって更に自然や環境に対して深い関心と理解が育まれ,農産物を単に価格ではなく環境保全型農業で作られた安全安心なものを選好するという消費者が育成されます。また,「田んぼの学校」では,生産者が消費者である参加者の志向を直接感じることも容易で,「田んぼの学校」の実施によって環境保全型農業にとりくむ意欲が育まれます。つまり,経済性よりも環境保全を優先する価値観を持った消費者と生産者を育成することができるのです。以上のことから「田んぼの学校」の推進は、持続的な農業の再生産による自然の循環の担い手を育成し、環境教育の目的である持続可能な社会の形成に資すると結論づけることができます(図3)。 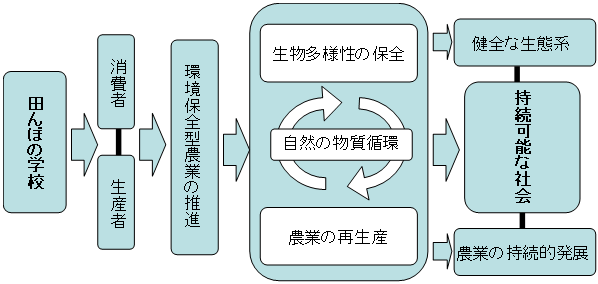 図3「田んぼの学校」による持続可能な社会へのプロセス (4) やはり子どもの時の体験が大切だ 5(3)で「田んぼの学校」による自然や農業体験には,関心(気づき)や理解(知る)を深める教育的効果の端緒がみられると述べましたが,今回の調査では大人と子どもの環境教育的効果の比較や近年研究の進歩の著しい大脳の働きとの関係までには至りませんでした。そこで、数学者の岡潔と脳生理学者の時実利彦が,子どもの教育の方法として興味深い分析をしているのを紹介します*17。 宮元 均 H22.4.8
*14 OECD(2004):「農業の多面的機能-政策形成に向けて」,荘林幹太郎訳,家の光協会,pp6 *15 農林水産省(2000):「図説食料・農業・農村白書(平成12年度版)」,(財)農林統計協会,pp11 *16 七戸長生・永田恵十郎・陣内義人(1990):「農業の教育力」,(社)農山漁村文化協会,pp33~41 *17 岡 潔(2001):「情緒の教育」燈影社,pp39~94 *18 時実利彦(1970):岩波新書「人間であること」,岩波書店,pp28~34 |
|