|
話題一覧へ |
地球環境時代の経済成長を考える
一方井誠治
3. エネルギー政策と気候変動政策の統合で経済発展をめざすドイツの挑戦
(エネルギー使用・温室効果ガスの排出とGDPとのデカップリング)
まずは最初に、以下の二つの図を見比べて欲しい。 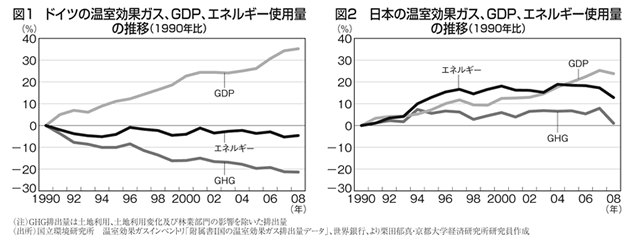 この図は、1990年から2008年までのドイツと日本におけるエネルギー使用量、温室効果ガスの排出量およびGDPの変化量を指数で表したものである。この二つの図からは、ドイツがエネルギー使用量を抑制し温室効果ガスを大幅に削減しつつ自国のGDPを増加させてきたことが読み取れる。これは現在世界が目指している、温室効果ガスの排出とGDPが切り離された、気候変動の面から見た「グリーン成長」に他ならない。それに対して、日本は相も変わらずエネルギー使用量と温室効果ガスの排出を共に増大させつつGDPを増加させてきたことが読み取れる。なお、世界的な景気後退をもたらした2008年のリーマンショックの影響がこれらどの指数でも日本では色濃く反映しているのにもかかわらず、ドイツでは比較的その影響が少なかったことも併せて読み取れよう。 ちなみに、ドイツはEUの加盟国であるが、京都議定書上、EU全体が負っている2008年-2012年の削減目標であるマイナス8%の削減目標をl達成するため加盟国がそれぞれ異なった目標値を域内で分担している中で、極めて大幅な削減目標値であるマイナス21%を引き受けている。そればかりか、ドイツは、国際的な温室効果ガスの削減枠組みの合意成立を待つことなく、既に2020年の自国の削減目標であるマイナス40%をすでに策定し、その達成に向けた各種の施策を展開している。 ドイツはなぜ、国際的な温室効果ガスの削減枠組みの合意を待つことなく、このような積極的な気候変動政策を行っているのだろうか。日本とドイツとのこれだけ大きな違いはどこから生じたのだろうか。 実は、ドイツが積極的な気候変動政策に転じたのはそれほど昔のことではない。1998年のシュレーダー政権の誕生以前のドイツは、当時のコール政権のもとで、日本と同様、産業界の意向に気をつかった保守的な立場をとっていた。そのため、野党が要求していた炭素税などは導入に至らなかった。しかしながら、シュレーダー政権の誕生とともに、連立政党としてはじめて政権に参加した緑の党の強いイニシアティブもあり、同政権は直ちに、エコロジー税制改革に着手した。エコロジー税制改革とは、エネルギーの使用抑制を通じて環境保全を推進するとともに、その税収を企業による雇用者の年金負担の補助にあてることにより雇用の増進を進めるという、二つの政策目標を同時に追求するいわゆる二重の配当政策である。 ついで、2005年には、一部産業界の強い反対はあったものの、欧州排出量取引制度に参加し、2008年には2020年までに40%の温室効果ガスを削減するための気候変動・エネルギー政策パッケージを策定した。この政策は関連する多くの法律の新規立法、改正を含むものであり、現在のドイツの政策の基本構造を支えるものとなっている。さらに、2010年には、2050年までの政策ロードマップである「エネルギー・コンセプト」を策定した。 私は、このタイトルが「気候変動政策ロードマップ」ではなく、「エネルギー・コンセプト」とされていることに強い衝撃を受けた。この内容を見てみると、気候変動政策はまさにエネルギー政策そのものであり、そのことはまさにドイツの経済政策そのものであるといえる。そのドイツのエネルギーの概念(コンセプト)を、現在の原子力と石炭を中心とするものから、抜本的な効率改善と再生可能エネルギーの導入の組合せに根本的転換していくことにより、ドイツの新しい産業や技術の排出を促し、新たな経済構造を作り、来るべき、気候変動が進み、石油などの資源・エネルギー価格なども高騰していく時代でも発展することが可能な経済へいち早く脱皮していこうとする、すぐれて戦略的な考え方に立っていることがわかる。ちなみに、このエネルギー・コンセプトはドイツの環境省と経済省が協同で作成したものである。 もとより、いわゆる低炭素社会経済への確立した道はなく、各国とも模索をしながらその方向を目指している。したがってドイツのこの戦略が将来にわたって100%成功する保証はない。また、EU経済における現下のドイツ経済の相対的な好調は、ドイツがマルクからユーロに移行した恩恵を受けているとの指摘もある。しかしながら、その背後には先に見たようなドイツの確固たる戦略があり、冒頭見たように、少なくともここ20年のGDPとGHG排出の動向を見る限り、ドイツにおいてはその戦略は他の要素とも相まって着実に効果を発揮しつつあるように筆者には思われる。 日本の気候変動政策の問題点対して、日本の状況はどうだろうか。日本は環境や経済の将来の動向をきちんと見通して、戦略的な対応を講じているのだろうか。これまで日本では、京都議定書の第一約束期間である2008年-2012年までに1990年ベースでマイナス6%の削減目標を達成すべく、温暖化対策推進法や同法に基づく京都議定書目標達成計画を策定し、各種の対策を講じてきているとされる。しかしながら、その実態は、最大の温室効果ガス排出量を有する産業部門では自主的な削減努力がその対策手段の柱とされ、また、一般家庭についても、温室効果ガス削減の国民運動が主たる対策となっていた。その一方で、経済に大きなインパクトを与える実効性のある炭素税や排出量取引制度などは、目先の経済に悪影響があるとの産業界の強い反対を背景に、これまで導入がなされてこなかったという経緯がある。
そのような状況を2009年の政権交代を機にEU型の積極政策に変えていくべく「地球温暖化対策推進基本法案」が作成され、その中に、2020年までに25%削減する目標、炭素税、排出量取引制度、再生可能エネルギーの固定価格買取制度などの政策手段を導入することが盛り込まれた。しかしながら、前回も述べたように、この基本法自体、まだ成立しておらず、また、2011年の夏にようやく成立した再生可能エネルギーの固定価格買取制度を除いては、法案で予定されていた個別の制度もいまだ成立していない。この間、日本は冒頭見たように、ドイツと異なりGDPの増加とともにエネルギー使用や温室効果ガスの排出も増大傾向にあった。その原因はどこにあったのだろうか。それを示唆するのが次の図である。 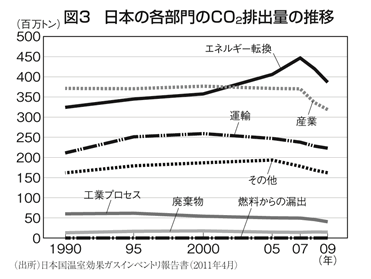 この図を見ると、他の部門と比べてエネルギー転換部門、すなわち発電所からのCO2排出量がこれまで一貫して増大してきていることがわかる。その理由は、実は石炭火力の増大にある。日本では、これまで原子力発電の割合を増大させることが国の方針とされ、それにより、電力の供給増大と温室効果ガスの削減を将来的に両立させるとの説明がなされてきていた。しかしながら、実際には原子力発電については、これまでも新規立地が地元の反対で遅れたり、中越沖地震などによる稼動率の低下があり、計画どおりには進んでこなかった。そのギャップを埋めていたのが、相対的に安いエネルギー源である石炭だった。そのため、家庭部門をはじめ多くの人々の努力にもかかわらず、日本全体としての温室効果ガスは増加傾向を止めることはなかったのである。 このことは、日本が温室効果ガスの削減に関して、あまりにも原発の増大計画に頼りすぎており、石炭火力などの化石燃料を再生可能エネルギーに着実に代替し、同時にエネルギー効率を高めることにより、エネルギー消費そのものを抑制していくという、気候変動政策の基本ともいうべき政策がおろそかになっていたことを意味すると筆者は考えている。 その結果、東日本大震災と福島の原発事故が起こると同時に、日本の気候変動政策は手詰まり状態を呈してしまったというのが現在の状況ではないだろうか。 問題は、これにとどまらず、先般閉幕した気候変動国連枠組み条約の締約国会議COP17において、日本が京都議定書の延長に強硬に反対し、何とか取りまとめられた国際枠組みにおいて、日本は削減目標を持つことを拒否するという事態に至ったことである。このような戦略が気候変動対策という観点から、また日本の経済の発展という観点から果たして賢明なものであるのだろうか。そのことについて次回は論じてみたい。 一方井 誠治 H23.12
|
|